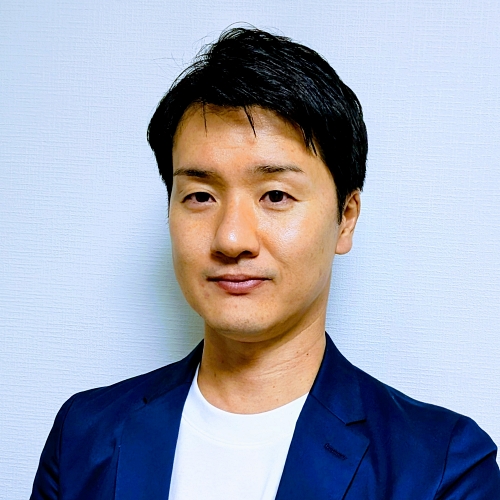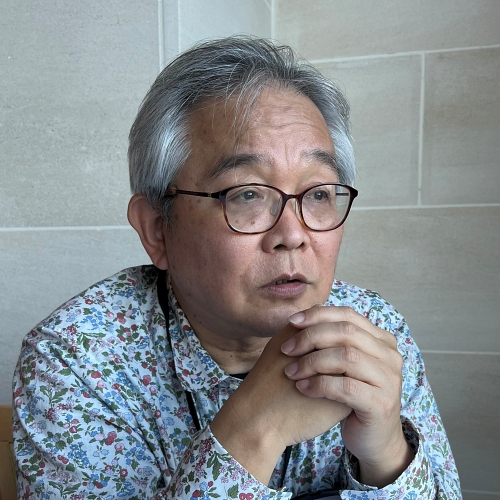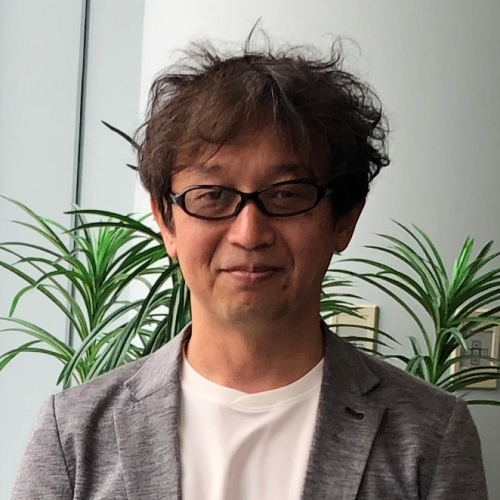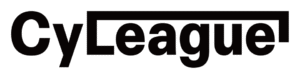リアルタイム:8月21日(木) 10:00〜16:10(予定) アーカイブ:各セッション終了1時間後~2025年9月21日(日)オンライン
DX&リスクマネジメントフォーラム2025
近年、地震・台風などの自然災害やサイバー攻撃、システム障害といったITインシデントが企業活動に深刻な影響を及ぼす事例が増加しています。さらに、サプライチェーンの多様化・複雑化や、経済産業省が警鐘を鳴らす「2025年の崖」に象徴されるように、ITシステムの老朽化・人材不足・サイロ化・ブラックボックス化といった構造的課題も顕在化しつつあり、企業は今まさに事業継続計画やセキュリティ対策の抜本的な対策を迫られています。こうした状況において、組織が主要な事業を安定的に継続させていくためには、事前対策の必要性の認識と十分な投資に加え、万が一ITが使えなくなった場合の具体的な復旧・代替策について、経営をトップに、全社横断で考え、教育・研修を通じた人材育成を行うなど、備えていくことが不可欠です。
本フォーラムでは、最新のリスク動向を踏まえ、IT-BCPの実践的な強化策と先進企業の事例を共有し、参加企業のレジリエンス向上を強力に後押しします。
事前申込+当日視聴アンケート特典
本フォーラムに事前申込の上、当日のリアルタイム配信をご視聴いただきアンケート回答いただいた方の中から各セッションごとに抽選で5名様に【Amazonデジタルギフト券1,000円分】を進呈いたします。
キーワード
Program
DX&リスクマネジメントフォーラム2025
IT-BCP再起動:デジタル時代のセキュリティとレジリエンス強化
~サイバーインシデント・自然災害・OTリスクへの備えと対応~
Outline
内容
リスク管理、DX、情報システム、サイバーセキュリティ、総務など管理部門の担当者・経営層向けオンラインセミナー
参加費
無料
※要リスク対策.com会員登録(無料)資料
8月21日(木)のリアルタイム配信時の視聴画面より各セッションごとに資料ダウンロードが可能
※事後の販売は行いません。リアルタイム配信
2025年8月21日(木) 10:00~16:10(予定)
アーカイブ配信
各セッション終了後おおむね1時間後から2025年9月21日(日)まで、リアルタイム配信と同じURLからご視聴いただけます。
主催
株式会社新建新聞社/リスク対策.com
視聴申し込みにあたって
本オンラインセミナーは、リスク対策.com会員が対象になります。
セミナー配信システムについて
本オンラインセミナー(ウェブキャスト)のシステムはON24 Inc.によって運営されています。視聴にご使用になるコンピュータが技術要件を満たしているかご確認ください。
https://event.on24.com/view/help/ja/index.html?text_language_id=ja